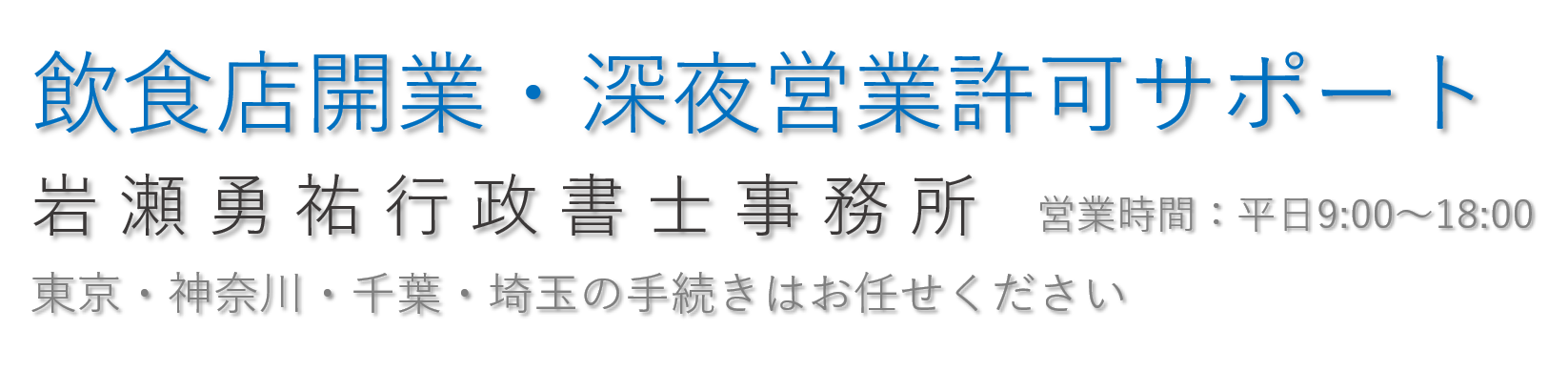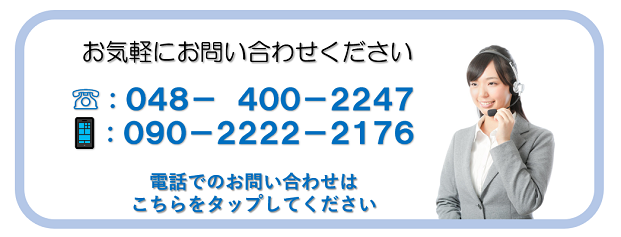当事務所では深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出手続きを専門業務として取り扱っています。
酒類提供飲食店を深夜の時間帯に営業する場合に深酒の届出が必要になります。
そもそも「酒類提供飲食店」とは何なのかを考えてみたいと思います。

飲食店営業と酒類提供飲食店営業
まず、飲食店営業を開始するためには、保健所で手続きをして「飲食店営業許可」を取得します。
飲食店を営業する上で必ず必要な許可になります。
この「飲食店営業」の中で、「酒類提供飲食店営業」に分類される営業形態があります。
酒類提供飲食店営業の意義について、警察庁生活安全局の解釈運用基準に詳細な記載があるので以下に引用します。
酒類提供飲食店の意義
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
(1)「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2)「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
「食事メインか酒メインか」というのが酒類提供飲食店営業に該当するか否かの分かれ目になりますが、居酒屋やダイニングバーでも主食に該当するメニューを豊富に取り揃えているお店もあります。
上記引用の「(2)イ」には「客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し」とあります。つまり、酒類を提供していても、「大半の客が食事をした後にすぐに帰るような店」は酒類提供飲食店には該当しないという事です。これに対して、主食を提供していても、「大半の客が酒を飲みながら長居できるような店」は酒類提供飲食店営業に当たるでしょう。
深夜における酒類提供飲食店営業とは
深夜とは「午前0時~午前6時」までの時間帯を指します。この時間帯に酒類提供飲食店営業をするためには、営業開始の10日前までに営業所の管轄となる警察署へ届出をする必要があります。
無届で営業をしていた場合の罰則は50万円以下の罰金となります。必ず事前に届出を済ませましょう。
そして、あくまでも「飲食店営業許可」の中で営業をするため、接待行為や深夜時間帯に酒類を提供しながら客に遊興させることはできません。深夜酒類提供飲食店営業をする場合は、風営法との兼ね合いをよく考え、違法営業とならなように気を付けましょう。
深酒の届出には店舗の平面図や求積図、設備図面を添付して警察署へ提出する必要があります。
当事務所では難易度の高い図面の作成を低価格で請け負っています。
お気軽にお問い合わせください。
飲食店営業許可・深夜営業許可手続きはお任せください
・スピード納品 ご契約から2日以内に納品可能
・居酒屋・バーなどの深夜営業届出に必要な図面作成 ➡ 40,000円 ~
・事前調査から警察署へ届出までのフルサポート ➡ 70,000円 ~
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
【東京都】
千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市
【千葉県】
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【埼玉県】
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。